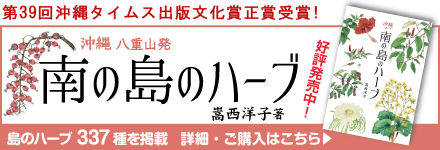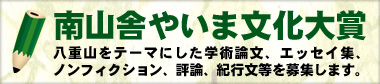有機農業に関心を持ち、堆肥を活用したパイン・マンゴー作りに取り組んでいる「㈱農園ファイミール」代表の池村一輝さん。昨年11月に行われた沖縄県青年農業者会議2024年度意見・プロジェクト発表にて最優秀賞を受賞されました。そんな池村さんに今回発表されたプロジェクトについて、また、理想の西表島の在り方についてお話を伺いました。
─「資源が循環し、産業がつながる西表島」と題したプロジェクトを発表されましたが、これはどのようなプロジェクトでしょうか。
現在、西表では家庭や観光産業から出る生ゴミの処理方法が問題になっており、この問題を解決するために「生ゴミBOX」というアイテムを活用して生ゴミを堆肥化しようというプロジェクトを発表しました。観光と環境と農業。この3つは全部つながっていて、観光が潤うとどうしても生ゴミがたくさん出るんです。そこで、観光や家庭から出る生ゴミを環境に負担を与えることなく堆肥に変えて、その堆肥が西表の農業で利用されることで環境が守られつつ農業の質が上がっていく。その堆肥で作られた農作物がまた観光や地域住民に還元される、という好循環が成り立つことで、自然を守りながらも経済につながっていくような地域づくりをしていきたいというのが今回発表したプロジェクトの大枠です。
─西表島における生ゴミ処理の現状
西表は石垣と違って生ゴミをゴミ収集業者が回収してくれないんですよ。消却炉はあるのですが、生ゴミは水分を含んでいるので完全に燃やすには焼却炉の負担が大きすぎるらしく、燃えるゴミの中に生ゴミを捨ててはいけないんです。なので、西表では「生ゴミコンポスト」という大きなバケツみたいなものが地域ごとに一つ設置されていて、島民はそこに生ゴミを捨てる。というのが西表島の生ゴミ処理の方法なんです。でも、このコンポストではちゃんと処理できておらず、箱の中で生ゴミが腐ってしまい、腐敗臭で住民のストレスになっています。
─生ゴミを堆肥化する活動について
生ごみを腐敗させないために「生ゴミBOX」と呼んでいるアイテムを家庭へ配布し、これまで地域のコンポストに捨てていた生ごみを、このBOXで処理する実験を行いました。箱の中にはあらかじめ「床材」という資材を入れており、日々の生ごみを床材と軽く混ぜ合わせるだけです。この床材の原料はもみ殻・米ぬか・落ち葉・赤土の4種類の原料を混ぜ合わせ、発酵させた資材です。BOXは一般的な収納ケースと同様のサイズですが、一般的な家庭から出る生ゴミの量であれば約2ヶ月近く生ごみを処理することが可能です。箱の中で腐らせることなく保管した生ごみを回収し、僕達農家の手によって本格的な完熟堆肥に仕上げる作業へと移ります。この2段階の工程を経て、完熟堆肥が仕上がります。現在普及している箱数は40個と全世帯の5%にも満たないですが、将来的には西表の全世帯へと普及させ、生ゴミを全て堆肥に変えることを目標に今後も活動を続けていきたいです。
─堆肥の使い方、理想の西表島について
出来上がった堆肥は農業利用することが最終的な目標です。ですが、まずは一緒になって生ゴミ堆肥化に携わっていただいた住民の方々に活用していただきたいと考えています。島内では家庭菜園で野菜を育てている方が多くいらっしゃいます。島内で手に入る堆肥が良質で美味しい野菜が作ることができれば「生ゴミBOX」へ興味、理解を示してくれる方が増えると思います。
結果的に西表で使用される化学肥料や農薬の使用量が減れば、自然への負担が減るだけでなく農産物の質の向上へ繋がることと信じています。厄介者扱いされていた生ゴミが堆肥という貴重な資源へと生まれ変わり、自然負担ではなく土地を肥沃にする。そして育った作物が地域へと還ってくる。そんな好循環を目指し、活動を続けていきます。
(月刊やいま 2025年1/2月号より)
〈池村 一輝 プロフィール〉
いけむら かずき(37歳)
1987年1月26日生まれ。
㈱農園ファイミール代表取締役。㈱西表でしか設立者。
船浦小中学校、八重山高校、東洋大学卒業。
大学卒業後は三重県、茨城県の農場にて有機農業を学ぶ。
実家のパイン・マンゴー農園を継ぐため、2011年に西表島に帰島。